
|
ベアリングへのオイルの効果
原文:yama@18
校正:しげぞー、eagle0wl
はじめに ベアリングにオイルが差されているのは当たり前だと思っている方も多いと思います。オイルは今も昔もヨーヨーのメンテナンスにおいて大切な役割を果たしています。 『ヨーヨーはなぜ回るのか?』で紹介したトランスアクセル方式(ベアリング内蔵型)のヨーヨーの多くが、ベアリング部にオイルを差して使用します。ヨーヨーを戻りやすくするために、さまざまなオイルを使ったりする工夫もなされていますが、わざと戻らなくするためにオイルを抜いてしまう、というメンテナンスも存在します。 レスポンスとしてのオイル ベアリングの中に存在する油分を取ってしまうことを脱脂といいます。脱脂前と脱脂後ではどちらが長く回るのかというと、実は脱脂後です。オイルは潤滑剤であるはずなのに回転力が落ちる理由は、オイルが回転の抵抗として作用してしまっているからです。しかし、この抵抗はヨーヨーのリターンには必要な力となります。 オイルを差したベアリングの場合 それでは、そのからくりを見てみましょう。ここでは、ファイヤーボールなどで採用されているナイロンベアリングを例にしています(Fig.1) (Fig.2)。
金属ボールベアリングの場合だと、オイルは軸ではなくベアリングのボールの抵抗として働き、回転を止める役割をします。 ドライ状態のベアリングの場合 次に、ドライ状態(=脱脂後の状態)のベアリングを見てみましょう(Fig.3)。
皆さんも、ファイヤーボールをプレイしているとオイルが切れて戻ってこないという状況を経験したことがあると思います。金属スペーサーのルーピング用メンテナンスでは、粘度の高いオイルを使用しますが、スターバースト等のレスポンス以外にオイルの抵抗を使ってヨーヨーを戻りやすくさせるためです。 ルーピングヨーヨーの戻りについて、さらに補足しましょう。 ヨーヨーの糸が伸びきったところでは、オイルの抵抗によって固定軸のヨーヨーのような動きをさせているのです。(画像4)のようにたるむのではなく、(画像5)のように固定軸のように巻き戻ってきているのです。これは『ヨーヨーはなぜ回るのか?』でも説明したオフストリングヨーヨーでのルーピングでも同様です。しかし、完全に固定軸状態になるわけではなく、かなり抵抗の強いトランスアクセル状態になるわけです。
Fig.4 のループよりも Fig.5 のループの方が、常に安定した動きをすることになります。 オイルの効果はベアリングの精度でも変わる 同じオイルでも、ベアリングの精度によって効果が変わります。 例として、ヨーヨージャム純正ベアリングと、それよりも精度の高いステンレスベアリングを比べてみます。その違いは、ベアリングの”あそび”です。同じ量のオイルを注入した場合に、ジャム純正の方が遊びが大きいぶん戻りが悪くなります。高精度ベアリングの方は遊びが小さい分、少量のゆるいオイルを使用したとしても戻りがかなり良くなります。
実はジャム純正ベアリングなら、引いて戻すメンテナンスでもプラスティック・ウィップ(戻りの良いヨーヨーでは難易度が高くなるトリックのひとつ)ができます。しかし、高精度ベアリングでは、同じ量のオイルを使用しても戻ってきてしまうため、プラスティック・ウィップができません。 ベアリング内部の様子を示したものを Fig.6 に示します(説明のため、若干大袈裟な図になっています)。 以前「ハードディスクの流体軸受けをヨーヨーに使えないか?」と提案した人ががいましたが、流体はベアリングの代わりに使って抵抗を減らすというよりも「音を静かにする」ための技術なので、ちょっと流用は難しそうです(流体の分子は、ミシンオイルのそれより大きいはず)。 可能性のある代替品は、マグネティックフローティング(磁気浮遊)でしょうか。これは、軸とベアリングとを磁気的な力で浮かせるもので、距離によって磁気密度が増えるため、オイルと同様の効果を得られるかもしれません。でも、仕掛けが大掛かりで常温超伝導でも実現しない限り、今の技術では70グラム程度のヨーヨーへの実装は難しいでしょう。 さまざまなオイル バンダイメインテナンスワセリン 暑いとすぐに潤滑切れを起こすため、いささか使いにくいです。  ダンカンルーブ 上記のバンダイメンテナンスワセリンに近いです。  ブレインリューブ 東急ハンズなどで購入できます。シングルハンドプレイ・ナイスペ(ナイロンスペーサー)用オイルとして十分に使えます。  トリフロースプレー(テフロン配合) トリフローだからという理由で使ってた人もいました。トリフローグリスも一世を風靡しました。  ジッポオイル ベアリングの脱脂で用いられる洗浄剤は、ジッポオイルやブレーキスプレーが定番です。  ミシンオイル 安さと入手のしやすさから一時期絶賛されました。油膜切れは早いですが、2000年〜2001年頃に起こった、引いて戻すメンテナンスから脱脂メンテナンスへの過渡期には活躍しました。 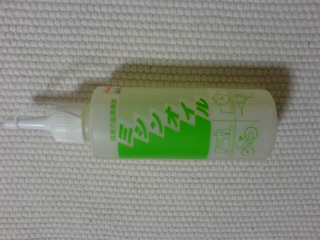 万能グリス ホームセンターなどで安価に入手可能です。2A(ツーハンドルーピングプレイ)スタイルで活躍しました。 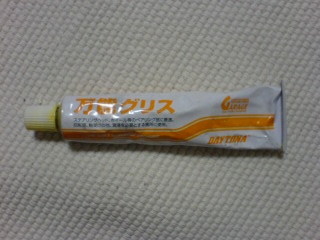 ラスペネ ちょっと値は張りますが、使っているプレイヤーも多いです。  21世紀(2006年時点)のヨーヨーオイル事情 ヨーヨー購入時は、ベアリングには錆び付き防止のためのグリスが封入されています。そのグリスをジッポオイルやブレーキスプレーなどの洗浄剤で脱脂します。脱脂後はラスペネなどの保護剤につけて保管します。 使用時には、もう一度洗浄剤で保護油膜を脱脂し、乾燥させたあとにそれぞれのオイルをつけます。 ※使用時にもう一度脱脂しているのは、保護油膜と使用オイルが混ざらないようにするためです。 プレイスタイルによるセッティングの違い 1A(ワンハンドストリングプレイ) 脱脂済みのベアリングを使うプレイヤーが多いです。ベアリング保護のため、わずかにオイルをさす程度です。ベアリングを保管する際にラスペネが使われることは多いです。 2A(ツーハンドルーピングプレイ) ナイスペレイダー(ナイロンスペーサーレイダー:ヨメガ社のレイダーをルーピングに特化させるメンテナンスの通称)には、ソフトなミシンオイルを少し差す程度です。 3A(ツーハンドストリングプレイ) バインドで戻すヨーヨーは脱脂済みのベアリングを使い、引いて戻すヨーヨーにはオイルを差して使います。 4A(オフストリングプレイ) 脱脂済みのベアリングを使うプレイヤーが多いようです。 5A(カウンターウエイトプレイ) 引いて戻すか、バインドにするかで選択肢が分かれます。プレイヤーのプレイスタイルによってセッティングが異なります。 20世紀のオイル事情 20世紀の事情は現在とは違っていました。当時はバインド技術(戻らないヨーヨーを強制的に引き戻す技術)が開発される前だったため、引いて戻るヨーヨーのセッティングが当たり前でした。 その当時、ほとんどのプレーヤーが行っていたメンテナンス方法を紹介します。 ベアリングが回らなくなってきたら脱脂します。脱脂後には大量にオイルをつけますが、使うオイルはプレイヤーやプレイスタイルによって異なります。 ワンハンド用に使われていたオイル ・ブレインリューブ
・メンテナンスワセリン ダブルハンド用に使われていたオイル ・トリフロー
・デュラエース
・セルマー
・ワセリン
・万能グリス
etc… 最後に 今やナイスぺ用の改造が当たり前となったレイダーですが、その当時はギャップ等の調整は不正改造と見なされていました(当時はバンダイが大会を主催していたため、バンダイ以外のヨーヨーは使用禁止・バンダイ製ヨーヨーであっても改造禁止でした)。無改造のレイダーやファイヤーボールを使わざるを得ない当時は、オイル選びはとても重要でした。 THP(Team High Performance:ハイパーヨーヨーブーム時に一斉を風靡した、ハワイのプロパフォーマンス集団。現在は解散)がトリフローグリスを使ってると聞けばみんなトリフローグリスを使い、セルマーのグリスがいいと聞けば楽器屋さんに走ったものです。そのようなグリスメンテもまた楽しいものでした。 このように、ベアリングオイルも時代によって、またプレイスタイルによっていろいろなものが使われ、それは今の時代にも受け継がれてきています。たかがオイル、されどオイルということで、ヨーヨーにおけるオイルの大切さがわかっていただけたでしょうか。 |